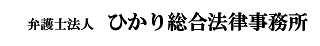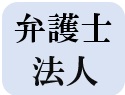建築訴訟の特質と紛争解決のプロセス
裁判所に係属する訴訟の中には、審理する上で比較的問題が少なく、円滑に進行する事件と、これとは反対に、当事者の主張・立証が錯綜し、その整理に難渋する事件とがあります。
後者の複雑・困難事件の典型としては、医療訴訟・建築訴訟・IT訴訟等が挙げられますが、これらは、紛争の把握・解明のために当該分野に関する専門的な知見を要することから、その導入のために専門家の関与を求めるほか、裁判官・訴訟代理人(弁護士)も専門的事項に関する知識の習得が必要となります。
このような訴訟の審理の特質については先に「専門訴訟と弁護士」と題するコラムを執筆していますので、そちらをご参照ください。
今回は、その中でも、私が比較的多く関与してきた建築訴訟を例にとって、実際の裁判の場で、複雑・困難性の解消のためにどのような方策が採られているかを説明します。
建築訴訟とは、その字句どおりに考えると、建物の建築又は建築された建物の取引を巡る紛争に関する訴訟ですが、上記のような問題点を抱えているのは、その中でも特に建築に関する専門技術的な問題が紛争の原因となっている場合です。
多くのケースでは、実際の建物が契約(具体的には契約に当たって準拠すべきものとされた設計図書)によって特定される性質・形状・性能を有しているかどうかが問題となりますので、建築に関する専門技術的な見地からの検討を踏まえた上で、建物が請負契約又は売買契約に適合しているかどうかが審理の命題(争点)となります。
契約適合性は、最終的には法律的判断事項ですが、その前提として建築技術上の欠陥ないし不具合が問題となるわけです。
また、建物の建築の過程では追加・変更工事が不可避ですので、当該変更部分の工事が有償か無償かが争われることも多く、当初契約の内容との照合、相当代金額はいくらかといった点についての検討が必要となります。
このような場合、審理に建築専門家に関与してもらい、技術的な事柄についての説明を受けることが必要な場面がしばしば生じます。
ところで、民事訴訟手続に関与する専門家としては、主として争点整理の段階において「専門的な知見に基づく説明を聴くために」(民事訴訟法92条の2第1項)選任される専門委員と、証拠調べにおいて「鑑定に必要な学識経験を有する者」(同法212条1項)として専門的な事項に関する意見を述べることを求められた鑑定人がいます。
このうち専門委員は、平成15年改正民事訴訟法によって初めて導入された制度ですので、それまでは代替的な措置として、訴訟係属中に民事調停に付し、各分野の専門家が調停委員として裁判官及び法律家調停委員とともに調停委員会を構成し、争点の整理と話合いによる解決に当たるという方法が採られていました。
これは、東京地裁のような大規模裁判所には調停専門部が置かれており、多数の専門家調停委員(医師、建築士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、IT技術者等)が配属されていたことから、他の通常部で審理されていた事件でも、調停部に回付して、調停事件として争点整理と話合いを行っておりました。
このような審理方式は、柔軟で使い勝手がよいことから、上記の専門委員制度が導入された後においても、引き続き利用されてきました。
そこで、審理(争点整理段階)における専門家関与の方法としては、訴訟手続により争点整理を行う際に利用される専門委員関与型と、訴訟をいったん調停に付した上で争点整理と話合いを行う専門家調停委員関与型があることになります。
それでは、この2つの方法はどのように使い分けられているのでしょうか。
訴訟を調停に付する場合であっても、話合いの前提としてまずは争点を整理する必要がありますから、専門家の説明を聴きながら、当事者の主張している欠陥ないし不具合が建築技術上どのような意味を持つか、工事内容が変わった箇所が当初契約の範囲に含まれない有償の追加・変更工事であるかどうかなどを検討することになります。
その際、例えば、瑕疵該当性については、建築資材の性質上ある程度のばらつきはやむを得ないこともあり、また、施工誤差として許される範囲の差異もありますから、この点に関する専門家の説明を聴取しながら、調停委員会として争点として取り上げるべき事項かどうかを選別していくことになります。
また、現状がどうであるかを見なければ判断できないことも多いので、ほとんどのケースにおいて現地調停を行い、実際の建物の状況を見分した上で上記の判断をすることになります。
特に、瑕疵(契約不適合)として主張されている箇所が数多い場合は、現地で実際の状況を見て、真に問題となる箇所を選別する必要があります。
調停は、機動性がありますので、このような手続に適しています。
そして、現地調査を経て、調停委員会は、瑕疵(契約不適合)として取り上げるべき欠陥ないし不具合を特定し、その補修に必要な費用を積算した結果に基づき、調停案を提示することになります。
しかし、調停は、基本的には話合いによる紛争解決制度ですから、当事者の対立が激しいため合意が成立する可能性がない場合にまでこの手続を利用することは相当でありません。
例えば、建物の構造に関わる重大な欠陥であることを理由に建物を建て替えるほかないと主張されているケース、建築現場において基礎構築のために掘削を行ったところ、隣地が地盤沈下し、あるいはその上の建物が傾斜したというような第三者被害型のケースでは、被害感情が大きく、話合いが成立する見込みはありません。
また、欠陥現象をもたらした原因が不明の場合(例えば、雨漏り)には、現場見分程度では真の原因を探求することは不可能ですから、結局は鑑定により破壊検査や機器検査をして専門家の意見を求めざるを得ないことになりますので、これも調停不相当です。
他方、専門委員は、アドバイザー的な立場で専門技術的事項について説明するための制度ですから、役割的には争点整理に関する限り、専門家調停委員と基本的な差異はありません。
また、建築訴訟の性質上、専門委員も現地調査をすることが多いことは、専門家調停委員と同様です。
もっとも、専門委員の関与の仕方が説明にととどまるべきか、場合によっては意見を述べることも許されるかは、議論されているところですが、実務上は事件の特質に応じて、当事者の意向をも聴取しながら、慎重に運用されています。
そうすると、建築訴訟においては、話合いによる解決が困難なため調停に付することができないケースを中心に専門委員関与型の審理が行われているということができます。
なお、調停に付したものの合意が成立に至らなかった場合には、訴訟手続に戻ることになりますが、調停の最終段階で調停委員が専門的知見に基づいて作成した意見書は調書に添付されることが多いので、その後の審理において書証として活用されることがあり、不調になったからといって、それまでの手続が無駄になるわけではありません。
以上のように事案の性質に応じて専門家が関与する方法は異なりますが、要は、紛争解決のために必要な建築技術に関する専門的知見を提供してもらうための方策の問題ですので、当事者としては、専門家に紛争の実相を正確に把握してもらうための主張・立証を尽くした上で、専門家の建築技術上の見地からの説明にも謙虚に耳を傾ける姿勢が必要でしょう。
以上