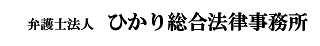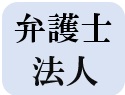裁判員裁判を契機に量刑決定過程を考える
1 裁判員裁判の法律施行から、早いもので、去る5月で、3年を経過した。裁判員を経験した市民の方々の感想は、概ねよいと伝えられている。これは、私は、ある程度予想していたところである。というのは、検察審査員を務めた人たちは、大概、よい感想で帰られると聞いていた。同窓会のようなものも出来ていると聞く。これは、推測するに、何人かでチームを組んで意見を交換し、協議をすることで、一体感を生じ、かつ、社会に貢献できる仕事を成し遂げたという達成感を味わうからではないかと思う。裁判員であれば、なおさらではないだろうか。困難な事件、長い時間をかけて職務を行うことは、大変な犠牲を払うことになるが、達成感も大きい、と思われる。もちろん、事件によっては、大変な心理的負担を負う場合があることは否定できない。
一方、受け入れた側の裁判官の感想が、7月18日付け読売新聞朝刊に掲載されていた。いずれも裁判員参加の意味を高く、積極的に、評価するものであった。事件についての見方が、裁判員が評議に加わることにより、多角的になり、かつ、深まること、一方、被告人が、判決を受けて、深く感銘する様子が見られる事例などが披露されていた。
2 以上のようなこともあってか、裁判所の側からは、現行制度の見直しを求める声は、それほどないようである。
3 被告人が起訴された事実を真っ向から争い、かつ、証拠としても、犯行を直接目撃した証言や被告人の自白という、いわゆる直接証拠がない事件、したがって、情況証拠から事実を認定するという、重大事件でも、すでに、裁判員裁判が行われ、判決にまで至った例がある。複雑困難事件で裁判員裁判がやれるのかという危惧がないわけではなかったが、関係者の協力が得られて、実施できたことは大きい。
4 一方、起訴された事実にそれほど争いがなければ、裁判所が決めなければならないのは、量刑である。この分野でも、裁判員の参加が、いくつかの新しい潮流ないし傾向を生み出しているようである。
一つには、性犯罪の刑が重くなったことである。市民の目からすれば、今までの刑が軽すぎたということであろうか。性犯罪は、その者の人格に深く根ざした行為であり、反復累行されることが多い。出所後の再犯率も高い。このようなことに重点を置いた結果かもしれない。
二つ目は、傷害致死罪であっても、殺人罪の刑と比べて勝るとも劣らない刑が科されることが、新聞報道で目に付く。人間の生命が失われたという結果を重視し、殺意が認められなくとも、それに匹敵するような悪質な事案であることを示しているのであろう。
以上は、現在のところの、厳罰化傾向を示す事例であるが、必ずしも、一方的傾向ばかりではないようである。新聞報道だけからであるが、従来なら、実刑になったような事案でも、保護観察を付けて執行猶予にするケースもあるようである。社会内での被告人の立ち直りに賭けてみたいという裁判員の方々の熱意が、伝わってくる。
5 それでは、判決するに当たり、量刑基準、その判断のための資料という点はどうなっているのであろうか。
現在のやり方では、基本的に、検察官が求刑をし、評議のときに、裁判員は、量刑検索のデータベースに基づく量刑の傾向を知らされて、意見を出し合い決定しているようである。最近の報道では、検察官の求刑を超える例も、ときどきあるようである。しかし、多くは、従来と同様に、検察官の求刑が上限の役割を果たしているようである。以上のやり方で、一応スムーズに量刑判断がなされているように見える。
以下においては、あえて、将来志向で見た場合の、2つの論点を指摘したい。
第一には、量刑を判断する資料が、裁判所に、十分提供されているかの問題がある。アメリカの例では、我が国と制度が異なるものの、量刑を決める前に、量刑に絞って、被告人の全体像が分かるような、かなり詳細な被告人の生育歴、経歴等の調査をし、これを検討の上、量刑が決定される。我が国では、少年事件において、家庭裁判所調査官により、処遇を決定する上での網羅的な調査がなされ、それが、処遇決定の資料とされる。刑事裁判において、量刑に関して、判断のための資料が少ないという声が、もし聞かれるとすれば、判決前調査制度の採用が検討されてしかるべきであろう。
第二は、先ほどの基準の問題である。検察官の求刑は、多少の地域差はあるにしても、ある程度、統一された基準に基づくものと推測され、既に述べたように、裁判所の量刑決定に当たり、実質的に、一定の基準としての役割を果たしている。しかし、そのような基準を、当事者である検察官のみの関与で作成してよいのかの問題がある。この観点は、従来、それほど意識されることはなかった。他方、量刑検索のデータベースもあくまでも、過去の判決の結果の集大成である。それは、量刑のおおよその傾向(あるいは一定の幅)を示すものではあっても、量刑のための具体的指針を、裁判員らに明示しているとは言い難い。とすれば、まず、量刑基準を裁判所なども入った機関で、オープンに議論して作成するという方向性が考えられる。英米でみられる、量刑ガイドライン制定の方向である。これにある程度の拘束性を認めることが考えられるが、あまり厳格なものにすることは、我が国に合わないかもしれない。
ところで、量刑ガイドラインの持つ、十分に意識されていないが、重要な役割は、刑を加重したり、減軽したりする要素とその加減の割合などをあらかじめ示すことにあるだろう。一例を挙げれば、減軽要素として、深く反省して罪を自白した場合には、刑を2割引にするとかが、アメリカでは行われているようである。ドライな感じを受ける向きがあるかもしれないが、このようなガイドラインをあらかじめ示すことにより、被告人側に、事前に、科される刑の予測をさせ、自白のインセンティブを作ること、さらには、有罪を認めて、量刑に合意をする手続(司法取引と呼ばれる)も将来的には検討してよいのではなかろうか。
いずれにしても、刑の加重・減軽の事由を取り出して、これをどの程度、量的に考慮すべきかという検討はせずに、すべて総合判断に任せているというのが、我が国の量刑決定の現状であるといってよい。どんぶり勘定のままでよいか、より数値化すべきかの問題といえる。
お隣の韓国は、基本的に我が国に近い制度であったが、最近、この判決前調査制度、量刑ガイドラインを取り入れる方向の改革をしたと聞く。その実施状況の紹介を待ちたいところである。
我が国においても、裁判員裁判の導入を契機に、量刑の手続において、既に述べたような観点からの、新しい制度設計を検討する時期に来ているのではないだろうか。
以上